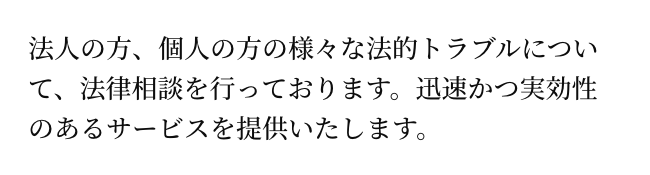刑事弁護
無罪判決の実績があります。
日本においては、起訴された場合に有罪となる確率は、99.9%とも言われています。
したがって、起訴された際に、おそらく被告人の犯行であろう、との先入観が生じ、犯行を否認している被告人の主張が精査されない危険性があります。
当事務所では、被告人の主張に耳を傾け、その主張を信じ、いわれのない罪を被せられることなく、適正な刑事裁判が受けられることを常に心がけ、弁護活動を行っております。
その結果、当事務所では、担当した刑事事件において、2件の無罪判決(一部無罪を含む)を受けた実績があります。
-無罪判決の事例紹介-
ひき逃げ(自動車運転過失致傷)での起訴
有力な証拠はなく、ただ被告人が事件後に、知人に送ったメールの内容が犯罪事実を認めているのではないかということが争点になりました。しかし、ひき逃げに使われた車両が、事件当時、複数人が乗車していたことを推認させる事実を主張したところ、被告人の犯行と認めるには合理的な疑いが残るとして無罪となりました(なお、別の日に、被告人が無免許運転をしていたことから、この点については、有罪となっています)。
傷害罪での起訴
マンションの一室において、被害者の顔面を殴打して怪我をさせた傷害罪で起訴されました。被告人は当初から犯行を否認しており、被害者及び被害者の妻の供述以外に有力な証拠は無く、2人の供述の信用性が争点となりましたが、尋問等が功を奏し、2人の供述には信用性が認められない為、被告人の犯行と認めるには合理的な疑いが残るとして無罪となりました。
~不当な身柄拘束・処分がされないために~
当事務所では、逮捕、勾留、起訴のそれぞれの段階で、早期に日常生活に戻ることができるよう、身
柄の解放に積極的に取り組んでいます。
逮捕されないための迅速な対応
逮捕するためには、「罪を犯したことを疑うに足りる相当の理由」のほかに「逮捕の必要性」が必要とされています。当事務所では、逮捕される可能性がある場合、被害者との示談交渉、捜査機関への事情説明、勤務先・学校への対応など、迅速かつ的確な弁護活動を行います。
-逮捕されなかった事例紹介-
- 電車内での痴漢を疑われ、逮捕されるかもしれない、どうしたら良いかとのご相談でした。当時の状況を細かくお伺いしたところ、逮捕手続がとられる可能性もあったため、まずは弁護人名で、管轄の警察署に事情の説明を行い、相談者に逮捕の必要性がないことを丁寧に説明したところ、逮捕手続はとられず、勤務先や家族等にも迷惑をかけることもなく、無事解決しました。
- 銀行口座を開設して売却してしまったため、自首したものの、今後、逮捕されるかもしれないとのご相談でした。警察には、逮捕の必要性がないことを説明するとともに、ご家族から、取調べの折には必ず出頭させる旨の誓約書を提出いただいた結果、逮捕されることなく捜査が進められました。
勾留請求しないための意見書
逮捕された場合、その大半が勾留請求をされています。そこで、検察官に対し、勾留請求しないように意見書を提出するのが有効な場合があります。当事務所では、意見書の提出が適切な事案かどうかの見極めを含め、迅速に対応いたします。
-勾留請求されなかった事例紹介-
- 交通事故で被害者が死亡したり、重篤な怪我をしたりした場合、軽微でも前科があると逮捕され、そのまま勾留されてしまいます(前科が無い場合は、逮捕はされますが、勾留はされない場合がほとんどです)。対人無制限の保険に入っていることなどを意見書で説明した結果、無事に勾留されませんでした。
- 逮捕され、弁護人が接見に赴こうとしたところ、警察署から被疑者が病院に行きたがっているという虚偽の事実を伝えられ接見を妨害されたため、検察庁に強く抗議したところ、翌日に釈放されました。
不起訴処分のために
不起訴処分となった場合は、捜査対象となった事件について、以後罪を問われることはなく、前科もつきません。そして、勾留されていた場合には、釈放され、日常生活に戻ることができます。
当事務所では、ご依頼頂いた事件について、詳しく事情をお伺いして、不起訴処分の可能性がある事案については、状況に応じて最善の方法を模索し、不起訴処分となるよう尽力いたします。
その結果、不起訴処分となった実績が多数ありますが、その一部をご紹介いたします。
-不起訴処分となった事例紹介-
- 万引きした事案において、被害店舗との間で示談が成立し、起訴猶予となりました(複数あり)。
- 電車内での痴漢行為について、逮捕当初から一貫して犯行を否認していたものの、起訴によるデメリットも大きかったため、犯行は認めない前提で示談交渉した結果、示談成立の上、不起訴処分となりました。
- 自身の勤務先で現金が盗まれたという窃盗の事案で嫌疑をかけられ、逮捕されたものの、逮捕当初から一貫して否認しており、取調べで何度も追及されたものの、否認を続けた結果、嫌疑不十分で不起訴となりました。
- 謝罪に訪れた人物に対して脅迫し、かつ土下座を強要した事案において、被害者の方との間で示談が成立し、起訴猶予となりました。
略式起訴
勾留されている事件で、通常の起訴がされた場合、起訴から判決の言い渡しを受けて裁判が終了するまでの約1か月半、更に身柄を拘束されることになります。一方で、略式起訴となった場合には、起訴された時点で釈放され、その後に裁判も開かれず、定められた罰金を納付すれば事件が終了します。罰金や科料が相当とされる比較的軽微な事案で、被害者との示談が成立するなど、有利な事情が望める場合には、略式起訴とするように検察官に働きかけることが、日常生活への復帰の近道となります。
実際に当事務所で扱った事件の中で、略式起訴となった事例の一部をご紹介いたします。
-略式起訴となった事例紹介-
- 万引きの後、追いかけてきた店員を振り払おうとして、怪我を負わせたということで、強盗致傷として逮捕されました。このまま起訴されると、大きな社会的制裁を受けることが予想されたため、被害者に被害弁償をする一方、検察官に意見書を書くなどした結果、窃盗+傷害ということで、略式起訴という結果となりました。
- 別れ話のもつれから、首を絞めたということで、殺人未遂として逮捕されましたが、殺人の故意を否定しつつ、深い反省を示していたところ、暴行罪ということで、略式起訴という結果となりました。
相談費用
相談料
1時間まで、5,500円(税込)となります。
弁護士費用(10%税込表示)
1.起訴(裁判)前の弁護活動
| 着手金 | 33万円 |
|---|---|
| 勾留取消 | 5万5,000円(請求) 5万5,000円(報酬) |
| 不起訴処分報酬 | 22万円(自白事件) 33万円(否認事件) |
| 略式起訴報酬 | 11万円 |
2.起訴された後の弁護活動
| 着手金 | 33万円(自白事件) 55万円(否認事件) | 起訴前から受任の場合は11万円(自白事件) 又は33万円(否認事件) |
|---|---|---|
| 保釈 | 5万5,000円(請求) 1万円(報酬) | 1回目の請求について費用はかかりません |
| 接見禁止準抗告 | 5万5,000円(請求) 11万円(報酬) | 1回目の請求について費用はかかりません |
| 執行猶予判決 | (事案に応じます) | |
| 無罪報酬 | 55万円~110万円 | 事案に応じます |
3.その他の弁護活動
| 示談報酬 | 11万円 16万5,000円(被害者の宥恕あり) | 被害者の宥恕とは「加害者を許す」「処罰を望まない」といった意思表示のことです |
|---|---|---|
| 実質的被害弁償 | 5万5,000円 | |
| 被害弁償供託手続 | 11万円 | |
| 接見日当 | 3万3,000円(名古屋市・江南市内) 5万5,000円(上記以外の地域) | 3回目までは費用はかかりません |
| 公判期日出廷日当 | 3万3,000円(名古屋市・一宮市) 5万5,000円(上記以外の地域) | 2回目までは費用はかかりません |
※裁判員裁判対象事件につきましては、別途ご相談させていただきます。
刑事告訴・刑事損害賠償請求
当事務所では、被疑者・被告人のための弁護活動のほか、刑事告訴、刑事損害賠償請求等の被害救済のための代理人活動も、数多く取扱っております。
どこに被害の相談をして良いか分からない、警察に相談したけれど、なかなか受理してもらえない、捜査の進展がないなど、刑事事件の被害に関してお悩みの方は、お気軽にご相談下さいませ。
事案やご要望により、女性の弁護士による相談応対もさせて頂きます。
以下に、取扱い事例の一部をご紹介いたします。
■告訴案件
- 性被害
- 業務上横領
- 詐欺
- 名誉毀損/侮辱
- 傷害 等
■刑事損害賠償請求
- 性被害
- 傷害 等
相談費用
相談料
1時間まで5,500円(税込み)となります。
弁護士費用(10%税込表示)
- 着手金 11万円~(※事案に応じます。)
- 報酬金 11万円~(※事案に応じます。)