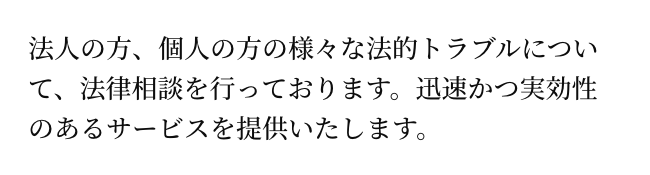労働トラブルは、早期対応が肝心
労働トラブルは、対応が遅れると以下のリスクが高まります。
- 労働者の嫌悪感情が増し、円満解決が困難になるリスク
- 労働基準監督署や労働組合の介入するリスク
- 訴訟対応リスク
- 他の労働者へも連鎖し、トラブルの大規模化につながるリスク
- 世間に公表され、企業の信頼やブランドイメージを損なうリスク
上記のようなリスクが拡大する前に、トラブルになりそうと感じた段階で、是非ご相談下さい。
当事務所では、弁護士と社会保険労務士が協働し、実戦的な解決策をご提案、サポートいたします。
【対応事例】
- 本採用拒否のトラブル
- 契約更新拒絶(雇止め)トラブル
- 無期転換ルール導入に関するトラブル
- 就業規則の不利益変更
- 労災事案の対応及び訴訟対策 等
本採用拒否
本採用拒否の問題とは
大多数の企業では、採用時に試用期間を設け、当該労働者の人物・能力等を評価して本採用(正社員)とするか否かを決定する制度をとっています。この試用期間満了後に、本採用拒否を行う場合、どのような理由があれば拒否できるのでしょうか。
試用期間の法的性質
そもそも、試用期間中の労働契約は、通常の労働契約と何か違うのでしょうか。
一般的に、試用期間中の契約には、社員が不適格だと使用者が判断した場合には解約できる旨の特約が留保されていると解されています。よって、試用期間が満了しても当然に契約が終了するのではなく、雇用契約を終了するには、解約権の行使が認められる必要があります。
本採用拒否(解雇権の行使)が認められる基準
判例は、本採用拒否が認められる基準として、「試用中の勤務状態等により、当初知ることができず、また知ることが期待できないような事実を知るに至った場合において、その者を引き続き当該企業に雇用しておくのが適当でないと判断することが、上記解約権留保の趣旨・目的に徴して、客観的に相当であると認められる場合には、先に留保した解約権を行使することができる」(三菱樹脂採用拒否事件 最判昭和48年12月12日)としました。
-本採用拒否に関する裁判事例の紹介-
本採用拒否が認められた事例
【日本基礎技術事件 大阪高判平24年2月10日】
技術者として採用された労働者の勤務態度の悪さを理由に行われた本採用拒否事例。 裁判所は、労働者が自身の勤務態度の改善が必要であったことを十分認識しており、改善に向けた努力をする機会も与えられており、指導・教育も受けていたことを指摘して、解雇をする前に告知・聴聞の機会を与えずとも、当該解雇は有効であると判断。
【日和崎石油事件 大阪地決平成2年1月22日】
給油所の見習いとして稼働していた試用期間中の者が、勤務中に歌を歌ったことについて上司から注意を受けるも改めようとしなかったり、客に対しての車の値段や行先を聞いたりするなどしてひんしゅくをかったり、店長の指導を聞かずに一方的に2時間にわたって抗議するなどしたため、勤務開始から8日目に解雇された事例。
裁判所は、勤務態度が、顧客へのサービスが要求される給油所の従業員としては適切なものとはいい難いことからすると、解雇権が濫用されたものとはいえないと判断。
中途採用者の本採用拒否については、新卒者の場合よりも、能力や適格性の有無が厳しく審査され、通常の解雇よりも緩やかな基準で解雇の有効性が判断される傾向にあります。
【ブレーンベース事件 東京地判平成13年12月25日】
パソコンのスキルがあると申告して採用された労働者が、FAX送信にも苦慮し、即戦力としての雇用継続が期待されないとして解雇された事例。裁判所は、職場が零細企業であったことを考慮して解雇を有効としています。
【アクサ生命保険ほか事件 東京地判平成21年8月31日】
金融機関での職歴の有無について履歴書に虚偽の記載をして採用された労働者の本採用拒否が問題となったが、裁判所は、労働者は採否決定の重要な要素に関して虚偽の申告をしたものであり、労使の信頼関係は破綻したとして解雇を有効と判断。
本採用拒否が認められなかった事例
【新光美術事件 大阪地決平成11年2月5日】
「未経験者可」の求人に応募し採用された労働者が、組合集会に参加した後に、些細な職務怠慢行為を理由に解雇された事案。
裁判所は、労働者は概ね誠実に職務を遂行しており、組合加入の有無等を聞かれた経緯に照らすと、本採用拒否に合理的理由は認められないとし、解雇を無効としました。
【医療法人財団健和会事件 東京地判平21年10月15日】
試用期間の途中で解雇された事案について「勤務状況等が改善傾向にあり、本人の努力如何によっては、残りの試用期間を勤務することによって改善する可能性もあったのに試用期間満了前に適性に欠けると判断して解雇したことは『解雇すべき時期の選択を誤ったもの』であり、本件の本採用拒否は合理的理由がなく、社会通念上相当とはいえないため無効」としました。
⇒ 試用期間は、労働者の資質、性格、能力等を十分に把握し、従業員としての適性を吟味するための期間であるから、試用期間の途中で労働者を解雇する場合には、試用期間満了後の解雇の場合よりも高度な合理性・相当性が求められます。
試用期間中に解雇する場合は、本採用できないと判断するだけの十分な理由があるかについて慎重に吟味する必要があります。
判断の注意点
本採用拒否の原因は、遅刻・早退・欠勤が多い勤怠不良のケースや、業務遂行能力の不足、非協調性、経歴詐称等があります。それぞれに本採用拒否が有効とされるために企業側が揃えるべき証拠や踏むべき手順・行動が異なるため、本採用をためらっている場合は、是非、当法人にご相談下さい。
契約更新拒絶トラブル(雇止め)と無期転換ルール
(1)契約更新拒絶トラブル(雇止め)
有期雇用契約と更新拒絶
労働契約に期間の定めがある場合には、期間の満了によって労働契約は終了するのが原則です。しかし、期間満了後も労働契約が事実上継続して長期間経過した場合や有期労働契約が何度も更新された場合に、更新契約の期間満了到来によって、原則通り終了させることができるのか?これが更新拒絶トラブル(雇止め)の問題です。
雇止めの有効性
企業側の更新拒絶が認められるかどうかは、従業員の更新への期待が客観的に存在し、法的保護に値するかを基準に判断されます。具体的には、雇用期間の性格により、以下の3類型に分かれます。
①正社員(期間の定めのない契約)と同視し得るケース
例)契約更新の手続き等を実施しておらず、無期と有期の区別が曖昧
無期契約における解雇権濫用法理が類推適用
→雇止めは解雇と同等の高いハードルが課せられます。
②正社員との区別は明確だが、更新期待があるケース
例)更新手続の契約管理がしっかり実施されていて、本人としても無期の認識はないものの更新回数が多く、臨時性のない業務で、この先も更新が期待される場合
→解雇権濫用法理が類推適用されるも、その基準は正社員とは「合理的な差異がある」と解されます。
更新の客観的な期待度により、類推適用される解雇権濫用法理とは異なります。
③更新への期待が客観的に認められないケース
例)当初から「更新の上限は3年まで」のように3年超の更新への期待がない場合
→原則として最後に更新した契約の期間満了で契約関係は終了。
ただし、同僚で同じく3年超は認めない契約をしていた者が例外的に更新されるケースがあれば、更新への期待は生じ得るので、注意が必要。
契約書作成実務の重要性
上記のとおり、有期雇用契約を反復更新後に終了させるためには、契約更新手続をきちんと実施すること、契約書面に期待を抱かせる内容を記載しないのみならず、管理者による発言(これまでに更新できなかった人はいない等)にも注意が必要です。
当法人では、貴社の業務内容、業務量等も勘案し、トラブルのない契約書を提案いたします。
(2)無期転換ルール
雇止め問題から労働者を保護するために無期転換ルールが法制度化されました(労働契約法第18条)
無期転換ルールとは、有期労働契約が反復更新されて通算5年を「超えた」ときに、労働者の申込みによって企業などの使用者が無期労働契約に転換しなければならない(使用者は転換権の使用を拒否できません)ルール のことです。
無期転換権行使の効果
- 申し込み:有期労働契約の通算期間が5年を超える場合、その契約期間の初日から末日までの間、無期転換の申込みをすることができます。
- 上記労働者の申し込みがあると、会社の承諾があるとみなされ(実際に承諾しなくても)、無期契約へと転換されます(契約期間が無期となるのみで、その他の労働条件に変更はありません)。
(3)具体的な問題
Q:無期転換後の契約は何歳まで?
(契約の上限期間や上限年齢を設定できるか?)
A:無期転換後は、正社員と同様、定年を設けない限り、契約が継続します。
また、定年を設ける場合、60歳以下で設定することができず、かつ、65歳までの雇用継続義務があることから、定年を60歳で設定した場合も、本人の希望があれば原則として65歳まで契約を継続(60歳以降は1年契約の更新で良い)する必要があります。
Q:定年再雇用と無期転換権の行使との関係は?
A:60歳で定年を迎えたあと、もしくは60歳を超えてから嘱託等で入社した従業員について更に無期転換権は適用されるのか?という問題があります。
原則:適用があります。
つまり、定年再雇用や60歳超の嘱託契約で、5年を超えて契約更新すれば、6年目以降に無期転換権が行使でき、無期契約に転換します。
例外:継続雇用の高齢者の特例
・適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主(特殊関係事業主含む)の下で、
・定年に達した後、引き続いて雇用される
一方、特殊関係事業主以外の他の事業主で継続雇用される場合には、特例の対象にならず、 無期転換申込権が発生することにご留意ください。有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)については、その事業主に定年後引き続いて雇用される期間は、 無期転換申込権が発生しません。
詳細は、厚労省のパンフレット参照 000818696.pdf (mhlw.go.jp)
Q:無期転換権発生前に、契約上限を設けることができるのか?
A:無期転換ルールの適用を意図的に避けることを目的として、無期転換権申し込み権が発生する前に雇止めをすることや、予め契約更新回数・年限に上限を設けることは、労働契約法の趣旨に照らし望ましいものではありません。
当法人へご相談頂ければ、諸問題に対応できる就業規則の作成・改正・運用をご提案させて頂きます。
就業規則の不利益変更
就業規則の不利益変更という言葉を聞いたことはあるかと思います。
ただ、言葉が独り歩きして、どのような場合でも不利益変更ができないと考えている方もいます。
適切な手続きを取れば、不利益変更をすることは可能です!
判例の立場・法律の内容
判例(秋北バス事件 最高裁昭和43年12月25日判決)は、
「新たな就業規則の作成又は変更によって、既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として許されないと解すべきであるが、労働条件の集合的処理、特にその統一的かつ画一的な決定を建前とする就業規則の性質からいって、当該規則条項が合理的なものである限り、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒否することは許されない」。と判示しています。
簡潔にまとめると、以下の通りになります。
労働条件を不利益に変更する場合、
| ■変更後の内容が合理的 | ⇒ | 労働者の(全体)同意なくして変更可能 |
| ■変更後の内容が不合理 | ⇒ | ①労働者の(全体)同意があれば適用可能 |
| ②労働者の(全体)同意なければ適用不可 | ||
| ↓ |
■変更後の内容が合理的 ⇒ 労働者の(全体)同意なくして変更可能
■変更後の内容が不合理 ⇒ ①労働者の(全体)同意があれば適用可能
②労働者の(全体)同意なければ適用不可
↓
現在この裁判例が労働契約法9条と10条に、明文化されています。
不利益変更の内容の合理性の判断基準
上記で述べた通り、就業規則の不利益変更が合理的かどうかは、不利益変更が認められるかどうかの判断の分かれ目になるため非常に大切です。ここで変更後の内容が合理的かどうかはどのように判断するのでしょうか。
例えば、みちのく銀行事件(最高裁 平成12年9月7日判決)は、「特に賃金、退職金など労働者にとって重要な権利、労働条件に関し、実質的な不利益を及ぼす就業規則の作成又は変更については、当該条項が、そのような不利益を労働者に法的に受任させることを許容することができるだけの高度の必要性に基づいた合理的な内容のものである場合において、その効力を生ずる」とし、その合理性の有無は、「労働者が被る不利益の程度、使用者側の変更の必要性の内容・程度、変更後の就業規則の名用自体の相当性、代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況、労働組合等との経緯、他の労働組合又は他の従業員の対応、同種事項に関する我が国社会における一般的状況等を総合考慮して判断すべきである」としています。
まとめると、以下のような項目を総合考慮して判断することとなります。
- 労働者の受ける不利益の程度
- 労働条件変更の必要性
- 変更後の就業規則の内容の相当性
- 代償措置その他関連する労働条件の改善状況
- 労働組合との交渉の状況
- その他の就業規則の変更に係る事情
就業規則を適切な手続きで不利益に変更するためには、不合理と判断されないために内容を吟味することはもちろん、従業員に対する真摯な説明なども必須です。 当法人にご依頼頂くことで、就業規則の変更を円滑に進めることが可能です。
労災事案の対応及び訴訟対応
疾病や精神疾患を原因とする労災事案お任せ下さい
工場で作業中に機械に腕を挟まれ負傷した、というケースは業務と負傷の因果関係(業務起因性といいます。)が明白であり、労災事故として認定してもらうこと自体は難しいことではありません。
しかし、精神疾患により退職せざるを得ないケース、脳梗塞や心筋梗塞等疾病により後遺症が残った場合や死亡に至った場合等、いずれも疾患や疾病と業務との因果関係の立証が困難であり、監督署へ労災申請しても簡単には認定されません。
また、因果関係が明らかであっても、過失相殺を主張され、十分な損害額が支払われない場合もあります。
社労士の役割
疾患・疾病に基づく事案については、客観的にこういう要件があれば業務起因性がある、と認められるための基準が厚生労働省から提示されています。
ただ、その認定基準の解読は容易でなく、その要件を満たすための資料収集、作成も細かな作業の連続で膨大な時間を要します。 そこで、労働分野に長けた社労士がご本人・ご家族よりヒアリング、資料を収集し、要件に沿った労災申請書を作成いたします。
弁護士の役割
重度の後遺障害が残る場合や死亡案件等、労災保険による補償だけでは実際の損害額を補填できない場合、弁護士が会社に対し、損害賠償請求の訴訟を提起いたします。
当法人は、精神疾患により死亡したケース、その他、複数の労災事案を扱った経験があります。是非、一度、ご相談ください。