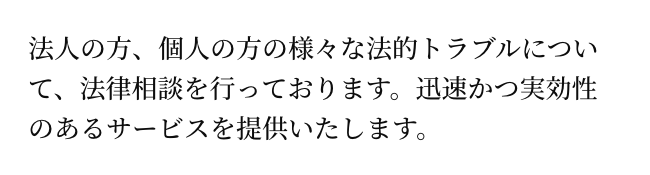弁護士、行政書士、社会保険労務士によるワンストップ対応
他国の法律に精通している法律事務所は存在しても、手続きに精通し、ワンストップで対応できる事務所は極めて少ないです。
当事務所では、企業規模にかかわらず、外国人労働者の雇用、海外での起業、国際取引の開始等の国際的な事業展開に際し、国際法務に精通した弁護士、行政書士及び社会保険労務士が一丸となり、国際取引に関する助言、雇用契約、在留資格の取得など、法的側面から様々なサポートをさせて頂きます。
具体的には、以下のようなサービスをご提供しております。
- 外国人労働者の雇用、在留資格(VISA)取得
- 従業員の海外出向
- 子会社・支店の設立手続
- 契約書の作成
- その他各種許認可の取得等
外国人労働者の雇用
日本人労働人口の減少により、今後も外国人労働者の受け入れが増加していくことが予想されます。
当事務所には行政書士、社会保険労務士が在籍しているため、外国人労働者の雇用の際にも包括的なサービスをご提供いたします。
1.在留資格(VISA)の取得
外国の子会社や関連会社から外国人労働者を日本に呼んで雇用する場合、就労可能な在留資格が必要になります。
具体的には「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「技能」、「高度専門職」のいずれかの在留資格が必要になります。
「技術・人文知識・国際業務」
営業・貿易担当者・SE等の技術者を雇用する場合。
「企業内転勤」
外国にある本店、支店、子会社や関連会社(以下「関連会社等」といいます)から日本にある会社に期間を定めて転勤し、上記「技術・人文知識・国際業務」に対応する業務を行う社員を雇用する場合。外国にある関連会社等に1年以上在籍している社員が対象となります。
「技能」
産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する社員を雇用する場合。例えば、中華料理の料理人やソムリエ、スポーツトレーナー、外国の建築技能を持った大工、航空機のパイロット等です。
※いずれの資格も単純労働をすることはできません。
「家族滞在」
「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「技能」等、就労系の在留資格を持つ者の配偶者及び子供を日本に呼び寄せて一緒に暮らす場合に必要な在留資格です。
「高度専門職」
高度外国人材の受入れを促進するため、高度外国人材に対し「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイント制を設け、ポイントの合計が70点以上の方が取得することができる在留資格です。
高度外国人材と認定されれば、5年の在留期間の付与、永住許可要件の緩和、配偶者の就労、親の帯同等出入国管理上の優遇措置を受けることができます。
「特定活動」
家族滞在に該当しない就労資格を有する外国人配偶者の養子縁組をしていない連れ子や事実婚のパートナーを日本に呼び寄せたいケースで取得できる場合もあります。
在留資格取得の流れ
日本の入国管理局に在留資格認定証明書交付申請を提出
↓
入国管理局が審査の結果、在留資格認定証明書を交付
↓
外国にいる招へい予定者に在留資格認定証明書を送り、在外日本大使館(領事館)で査証手続
↓
社員として日本に入国し、就労開始
当事務所の行政書士は、入管法施行規則の規定に基づき入国管理局へ届出をした申請取次行政書士ですので、外国人ご本人や会社のご担当者が混み合っている入国管理局に行く必要はなく、代わりに在留資格に関する申請書の提出を行うことができます。また、当事務所の行政書士ならオンライン申請も可能ですので、遠方のお客様のご依頼も受任できます。
2.社会保険について
在籍出向の場合
■ 資格
海外企業との雇用契約が継続している中で日本に出向してきた場合(技能実習生を含みます)、日本国内の企業から給与が支払われている限り、健康保険・厚生年金ともに被保険者資格を取得します。
ただし、厚生年金につきましては、社会保障協定を締結している場合、日本の厚生年金への加入は免除されます(健康保険のみ加入)。
■ 保険料
保険料につきましては、原則として、国内で支払われた給与分は全額が社会保険料の算定対象となります。
■ 健康保険証の使用
日本国内での療養に健康保険を使用した場合には、日本人と同様に扱われます。
移籍出向の場合
海外企業との雇用契約が解除され、日本国内の企業において雇用される移籍出向の場合には、健康保険・厚生年金ともに被保険者資格を取得し、日本人と同様に扱われます。
3.雇用保険について
外国人労働者は、原則的には被保険者資格を取得します。
ただし、労働者が自国で雇用保険制度に加入していることが明らかな場合は、日本において改めて加入しなくても良い場合があります。
4.労災保険について
外国人労働者は、日本国内の労災保険制度に加入することになり、日本人と同様に扱われます。
5.技能実習生について
■技能実習生と社会保険・雇用保険・労災保険
外国人技能実習制度とは、日本の技能、技術又は知識の開発途上国への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とした制度です。
技能実習生とは雇用契約の締結が義務づけられており、社会保険・雇用保険・労災保険の加入についても日本人と同様の取扱いとなります。
在留資格取得の費用
| 手続 | 着手金 | 報酬金 | その他実費 |
|---|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 (経営管理以外) | 5万5,000円~ | 5万5,000円~ | 翻訳料 |
| 在留資格認定証明書交付申請 (経営管理) | 8万2,500円~ | 8万2,500円~ | 翻訳料 |
| 在留資格変更申請 | 4万4,000円~ | 4万4,000円~ | 4,000円(印紙代) 翻訳料 |
| 在留期間更新申請 (転職を伴う場合) | 2万7,500円~ | 2万7,500円~ | 4,000円(印紙代) 翻訳料 |
| 在留期間更新申請 (転職がない場合) | 1万1,000円~ | 1万1,000円~ | 4,000円(印紙代) 翻訳料 |
| 在留特別許可(出頭の場合) | 11万円~ | 11万円~ | 翻訳料 |
| 在留特別許可(収容の場合) | 16万5,000円~ | 16万5,000円~ | 翻訳料 |
| 上陸特別許可 | 11万円~ | 11万円~ | 翻訳料 |
- 10%の税込金額を記載しています。
- 翻訳料は必要に応じて発生するものです。
- 在留資格の取得以外の費用につきましては、別途ご相談させていただきます。
よくあるご質問
従業員の海外出向
海外で事業を展開する際には、現地労働者を雇用するだけではなく、自社の社員を海外へ派遣する必要があります。
その場合の社会保険、雇用保険、労災保険はどうなるのでしょうか。
1.社会保険について
在籍出向の場合
■資格
社員が自社に在籍したままで出向する場合、日本国内の企業から給与が支払われている限り、被保険者資格は継続します。
■保険料
原則として、国内給与分は全額が社会保険料の算定対象となります。
ただし、例外として海外企業から支払われている給与を実質的に国内企業が負担していると認められる事情がある場合は、その給与についても社会保険料の算定対象となります。
■海外での健康保険の使用
海外で治療を受け、健康保険を使用した場合、日本の健康保険から治療費用が一部支給されます。ただし、この場合に支給される療養の範囲は、日本において保険診療の対象となるものに限定されます。
さらに、日本で受診した場合に発生する療養費を基に算定しますので、場合によっては、3割以上の費用負担となる場合があります。
また、海外では日本の保険証が使用できないため、病院の窓口では本人が一旦全額を負担し、後日、海外療養費を請求して還付を受ける仕組みとなっています。
還付手続は事業主経由で行い、還付金も事業主が代理で受領することができます。
■社会保障協定 ~厚生年金に特有の制度~
厚生年金特有の制度として、社会保障協定というものがあります。
在籍出向で海外へ赴任する際、赴任者は日本国内において厚生年金に加入するのはもちろん、原則として赴任先の国の社会保障制度にも加入する必要があります。
しかし、滞在期間が概ね5年以内の場合に限り、日本と赴任先の国との間で協定を締結することにより、赴任先での社会保障制度加入を免れることが可能です。
移籍出向の場合
■資格
自社との雇用契約を解除し、現地法人へ移籍した上で出向する場合には、日本国内企業との雇用関係がない以上、被保険者資格は喪失します。
■国民年金の任意加入
資格喪失後であっても、国民年金の第1号被保険者として任意加入することが可能です(ただし、海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人)。
2.雇用保険について
■資格
自社との雇用関係が継続する限り、日本国内の企業から給与が払われていなくても被保険者資格も継続します。
■保険料
国内企業から支給される賃金のみにかかります。
■失業給付(算定対象期間)
原則として、離職時前2年間で12ヶ月以上の被保険者期間があることが、失業給付の受給要件です。ただし、海外赴任により国内給与が0円である期間が30日以上ある場合は、0円であった期間が2年に加算され、その期間内で被保険者期間が12ヶ月あれば、失業給付の受給要件が満たさ れます(受給要件の特例の緩和措置)。
3.労災保険
労災保険は、社会保険、雇用保険とは異なり、属地主義を採用していることから、海外赴任の場合には補償の対象外となります。
もっとも、海外派遣の特別加入制度を活用すれば、補償を受けられる可能性があります。
社会保険等に関する相談費用
弁護士・社会保険労務士と共同でのご相談
1時間まで 5,500円、以降30分毎に5,500円となります。
その他の費用については、ご相談内容を伺った上で、お見積りをいたします。
子会社・支店の設立手続
外国会社が日本に事業拠点を設置する手段として、主に3つの方法があります。
①外国会社の日本支店
外国会社が日本に拠点をおいて継続的に営業活動を行おうとする場合、日本における代表者及び営業所となる場所を定めて支店(営業所)の設置登記が必要となります。
②子会社
日本に外国会社の子会社として株式会社又は合同会社等の設立登記が必要となります。
③駐在員事務所
上記①②と違い、日本国内での収益を伴わない活動に限定され、事実上、国内の取引先企業との契約業務や支払などの営業活動は行えません。そのかわり登記は必要ありません。
業務例)本国会社への情報提供、広告・宣伝、市場調査等
①②の違いについて
| 登記種類 | ①外国会社の支店(営業所) | ②外国会社の子会社(支社) (※株式会社の場合) |
|---|---|---|
| 登記 | 必要 | 必要 |
| 登記に関する 諸費用 | 登録免許税 9万円 宣誓供述書認証代 | 公証人役場 約5,200円 収入印紙 4万円(※) 登録免許税 15万円 |
| 資本金・ 投下金 | 不要 | 1円以上 (但し、資本金が少額過ぎると、取引先や銀行からの信用力や入管での申請に不利になる可能性があります。 代表者が「経営管理」のVISAを希望する場合は500万円以上が必要です。) |
| 会計処理 | 本国所得との合算処理が可能。 (但し、日本での税務申告必要。) | 日本法人の会計処理で完結 (本国とは別に行う。) |
| 法人名の制限 | 親会社と同じ社名で登記 | 制限なし (但し営業所、支社等は使用できません。) |
| 必要な書類等 | 【外国本国で用意するもの】 ・本国法人の登記されていることを証する公的書類と日本語の翻訳文 ・宣誓供述書 【日本で用意するもの】 ・日本支店代表者個人の印鑑登録証明書 ・日本支店の代表者印 | 【外国本国で用意するもの】 ・本国法人の登記されていることを証する公的書類と日本語の翻訳文 ・本国法人の定款と日本語の翻訳文 ・本国法人の印鑑証明書の公正証書 又はサイン証明 【日本で用意するもの】 ・日本子会社役員の個人の印鑑登録証明書 ・日本子会社の代表者印 ・出資金を入金するための日本の銀行預金通帳 |
| 取得可能 在留資格 | 【代表者】 企業内転勤、 技術・人文知識・国際業務、 (経営管理) 【社員】 企業内転勤、 技術・人文知識・国際業務、 技能 | 【代表者】 経営管理 【社員】 企業内転勤、 技術・人文知識・国際業務、 技能 |
- 電子認証の場合、4万円の収入印紙代は発生しません。
相談費用
子会社・支店の設立手続に関するご相談
弁護士・行政書士と共同でのご相談
1時間まで 5,500円、以降30分毎に5,500円となります。
その他の費用については、ご相談内容を伺った上で、お見積りをいたします。
契約書作成
海外の企業と契約を交わす際には、法律や商慣習の違いによりトラブルが生じる可能性がありますので、日本国内の企業との間で契約を締結する場合以上に契約書を作成しておくことが重要になります。
その際、どこの国の法律に準拠して契約内容を確定するかは、非常に重要で、後にトラブルが発生した際に多大な影響があります。
例えば、取引の中で問題が発生し、当事者間では解決できず、裁判所の判断に委ねざるを得なくなった場合に、どの国の裁判所で判断してもらうのか(国際裁判管轄)、というところから問題となりかねません。
また、仮に日本の裁判所で裁判が開かれることになった場合には、日本の法律を基礎として問題の解決を図ることになりますが、日本の法律上は、契約の内容・効力については、基本的には、契約当時に、当事者が選択した国の法律により判断される、と規定されています。
外国法に準拠した契約内容としてしまいますと、その国の法律を隈なく調べない限り、予想外の結論となってしまう恐れがあります。
そこで、当事務所では、トラブルが生じた場合に、日本において法的解決が図りやすいよう、日本法に準拠した契約書の作成をしております。
費用
契約に関する相談
1時間まで 5,500円、以降30分毎に5,500円となります。
契約書作成
16万5,000円~
具体的な費用については、ご相談内容を伺った上で、お見積りをいたします。